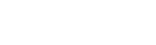国字本仮名草子『伊曾保物語』中卷第三六に、當時の常言に「鳩を憎みて豆を作らぬ」という。意味合いは、小さいことに拘り、大事なことを見失ってしまった結果、損することへの戒めとして珠玉なことばの一語として遺され、補助資料に示したように現行の国語辞典にも掲載されてきている。そして、鳩は人との関わりのなかで平和の象徴として人々に描かれもし、また伝書鳩のように人の役立てともなっている。だが、鐵道の駅や学校などの公共の建物の隙間に巣を構え、糞害も問題となったりする。彼らの主要な食べ物は豆で、これを求めて種豆蒔く畑に降り立つ。
これを寺田寅彦『歳時記新註』鳩吹に云う、古書には「鳩をとるとて手を合せて鳩の声のようにふきならすなり」とある。雄鳩の鳴き声に真似て鳩をおびき寄せ此を捕まえ、鳩舎でその習性を観察し飼い慣らした。大きな役割は脚に管を取り付け、遠くより此の中に手紙を容れ飛脚以上に着実に伝言を果たさせてきた。異国ドイツの諺に「屋上の鳩は手中の雀に如かず」と云うが此も咄嗟に使いたいとなれば手近の温め鳥なのか。
この鳩の鳴き声は、楠山正雄『物のいはれ』鳩に、「子鳩はよけい親鳩をこいしがって、ぽっほ、ぽっほといつまでも悲しそうになきました。」表現する。坂口安吾は『ジロリの女』で、「美代子さんのような可憐な小鳩を敵に廻しちゃ、私も地獄へ落ちなきゃならない。」と美代子という女人を「可憐な小鳩」に譬えたりする。はたまた、柳田国男『海上の道』に引いた、「柳田国男『海上の道』の一文「その頃がちょうど鳩麦煎餅(はとむぎせんべい)という、紙の筒に入った丸い煎餅の、人気に投じて盛んに売り弘(ひろ)められた時で、その製造元は爰(ここ)から五、六里の、たしか鳩崎という小さな町にあった。」の鳩麦煎餅に向かう。
鳩と云う鳥は、人にとって身近な生き物であり、人は良きにつけ悪しきにつけ、この鳥を介して物事をこなしてきた。都会の上空を滑空旋回する鳩の群れを仰ぎ見ながら、吾人の脳裡であの鳩という鳥が思いをふくらませている。人が生き物を飼うも、己れが叶わぬ眼前の空を舞う、軈て身近に戻てくる彼らを忘れてはならない氣がする。こう書き続けた吾人も小学生、中学生の頃、鳩小屋をこさえて数羽の鳩を飼っていた思い出が次つぎと蘇ってきた。玉蜀黍、向日葵の種など混ぜた餌を与えていたなぁ。
《補助資料》
小学館『日本国語大辞典』第二版(『故事俗信ことわざ大辞典』)
親見出し「はと【鳩・鴿】」はとを憎(にく)み豆(まめ)を作(つく)らぬ
畑に豆をまけば鳩がそれをついばむので、それを憎んで豆を作らない意から、わずかな事にこだわって必要なことまでもしないために、自分にも世間にも損害を招くことのたとえにいう。鳩懲らすとて豆まかぬ。*仮名草子・伊曾保物語〔一六三九(寛永一六)頃〕中・三六「ことわざに云(いはく)、鳩をにくみまめつくらぬとかや」*俚言集覧(一八一八(文政元)頃)「鳩を憎み豆つくらぬ」*日本俚諺大全(一九〇六(明治三九)~〇八)「鳩(ハト)を憎(ニク)んで豆(マメ)を作(ツク)らぬ」
【類句】鳩を懲らすとて豆蒔かぬ「鳩を憎み豆を作らぬ」に同じ。*俳諧・世話尽=世話焼草(一六五六(明暦二)年)曳言之話「鳩(ハト)こらすとて豆(マメ)まかぬ」
でんしょ-ばと【伝書鳩】〔名〕(1)ドバトの改良種で、訓練して通信に利用する鳩。原種はカワラバトとされ、その帰巣本能を利用したもので、実用通信距離は約二〇〇キロメートル。新聞社などの通信用のほか軍事用としても使われたが、現在では鳩レースなどに利用されている。レース鳩。*高知日報-明治二一年〔一八八八(明治二一)〕八月七日「軍事上に伝書鳩を使用することは広く世間に行はれ」*抒情歌〔一九三二(昭和七)〕〈川端康成〉「伝書鳩を愛の使者につかった恋人がありました」(2)毎日、会社が終わると、寄り道をしないでまっすぐに家に帰る男のたとえ。【発音】〈なまり〉レンショバト〔岐阜〕〈標ア〉[バ]〈京ア〉[ショ]
寺田寅彦「古書云」は、京都大学本『和歌集心躰抄抽肝要』〔大學堂書店刊六五頁15行目〕に、「鳩吹皆秋也。鳩吹儀多鳩ヲ吹テ取ヲ云リ葉與吹トハ草木ノ色付ヲ云リ。只秋ヲモ云」とある。