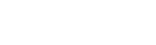夜空の星々を見上げて「天河」に△形に明るい星を線でつなぐ。右に彦星=牽牛星(わし座一等星アルタイル)、左に織女星(こと座一等星のベガ)、其の頂点にはくちょう座デネブ(Deneb の語源は、「めんどりのシッポ」)で夏の大三角(形)とし、「サマートライアングル(The Summer Triangle)」と見立てられてきた。茲に天の河が白く流れているように地上から捉えることができる。その星と星を結ぶ線刻模様画が九州吉野ヶ里遺跡の貴人埋葬の石棺蓋に描かれていると云う報道があったことで再び注目された。その古え人と東方天空の世界が今のわたしたちに何を伝えて何を見せてくれているのだろうか。明日は愈々「七夕」(旧暦で祝う地域もあるが)、「天の河」は夏だけの風物景ではない。冬の夜空にも見えている。紀貫之は『圡左日記』の一月の条に、「照る月を見れば流るるゝ天の河いづる湊は海にざりにける」と歌にしている。とは言え、ギリシャ神話の「ミルキィーウェイ」(写真図中央縱に白く見える。国立天文台写真画像)となっている。
此の夜景、天空の誘いを人々は常に語らいて物語、お咄し、神話へと発展させてきた。人々の暮らしに或る事物に夢が語られ、地上の万物が糸撚りの織物のように見事にまで接触し、新たな物事になっていくから不思議だ。二星はたかが肉眼で捉えられる距離、往き来も渡し舟で十分いける。されど宇宙旅行となれば織姫と彦星の隔てる距離は何と一四、四二八光年、此の距離を一夜で渡りきる発想、更にしのつく白雨が降るとなれば、舟では渡りきれず、軈て神さまは鵲という鳥が羽を広げて橋をつくり、二星が橋を渡って逢うことを考案したりするから不思議な時空間となる。此の鵲(かささぎ)も人なつっこい鳥で、障子を空けておくと、部屋のなかに遊びに来ると長谷川時雨がその随筆に述懐している。
 「七夕」の餝り室礼(しつらい)で準備した翌日には、若者は市街に浴衣着でくり出し、「酸漿市(ほおずきいち)」(愛宕神社、浅草寺)にて各々見合った竹籠状の庭上空間植物をもち帰る。なかでも「ほおずき」は橙色から赤色と「あかかがち」として親しまれてきた。観賞用もあれば食用もある。江戸の絵師、葛飾北斎が描いた若き女人が口に咥える図絵はその風情をものの美事にくっきりと伝えている。よく指で揉み解した酸漿の実をするっと呑み込んで、残った皮で袋状の笛づくりをする。巧く作り得た最初の子が鳴らす「ぶぅーぶぅー」という音色が懐かしい。「鬼燈笛」とは良くも言ったものだ。
「七夕」の餝り室礼(しつらい)で準備した翌日には、若者は市街に浴衣着でくり出し、「酸漿市(ほおずきいち)」(愛宕神社、浅草寺)にて各々見合った竹籠状の庭上空間植物をもち帰る。なかでも「ほおずき」は橙色から赤色と「あかかがち」として親しまれてきた。観賞用もあれば食用もある。江戸の絵師、葛飾北斎が描いた若き女人が口に咥える図絵はその風情をものの美事にくっきりと伝えている。よく指で揉み解した酸漿の実をするっと呑み込んで、残った皮で袋状の笛づくりをする。巧く作り得た最初の子が鳴らす「ぶぅーぶぅー」という音色が懐かしい。「鬼燈笛」とは良くも言ったものだ。
「ほおずき」を和藥で伝えるとき、漢語「酸漿」と云い、「洛神珠」と伝えてきた。軈て室町時代になると、「鬼灯草」や「鬼灯」と書かれ、今も此の初夏を彩る風物詩となっている。ひとときの涼感の憩いを感じさせる湿草植物なので、朝の水遣りをしつつ観賞用にも快適空間を造り出してれよう。そして、東の夜空見上げて星々に吾が心を投影する時間を大切にしたい。
《補助資料》
小学館『日本国語大辞典』第二版
あま-の-がわ[‥がは]【天川・天河】〔名〕(古くは「あまのかわ」とも)(1)銀河の異称。天空の川に見たてる。七月七日の夜、牽牛と織女がこの天の川を渡って年に一度逢うという、七夕の伝説が有名。銀漢。天漢。《季・秋》*万葉集〔八C後〕一五・三六五八「夕月夜(ゆふづくよ)影立ち寄り合ひ安麻能我波(アマノガハ)漕ぐ舟人を見るが羨(とも)しさ〈遣新羅使人〉」*十巻本和名類聚抄〔九三四(承平四)頃〕一「天河 兼名苑云天河一名天漢〈今案又一名漢河 又一名銀河也 和名阿万乃加波〉」*源氏物語〔一〇〇一(長保三)~一四頃〕東屋「あまのかはを渡りても、かかる彦星の光をこそ待ちつけさせめ」*日葡辞書〔一六〇三(慶長八)~〇四〕「Amanogaua(アマノガワ)」*俳諧・奥の細道〔一六九三~九四頃〕越後路「荒海や佐渡によこたふ天河」(2)「たなばた(七夕)」、また「たなばたまつり(七夕祭)」のこと。
*雑俳・柳多留-一八〔一七八三(天明三)〕「四方からふでをつっこむ天の川」*雑俳・柳筥〔一七八三(天明三)~八六〕一「白い短冊はまま子の天の川」【発音】アマノガワ〈なまり〉アマスガー〔八丈島〕アマネガワ〔津軽語彙・岩手〕アマノカワ〔長崎〕アマンカワ・アメノカワ〔熊本分布相〕〈標ア〉[ノ]〈ア史〉平安・鎌倉○○○●○〈京ア〉[ノ]【辞書】和名・色葉・名義・和玉・文明・伊京・明応・天正・饅頭・黒本・易林・日葡・書言・ヘボン・言海【表記】【天河】和名・色葉・名義・伊京・明応・天正・饅頭・黒本・易林・書言・言海【銀河】名義・伊京・天正・易林【銀漢】色葉・名義・天正・書言【漢河】色葉・名義【天漢】文明・伊京・ヘボン【銀璜】色葉【漢】和玉【銀浦】伊京【銀潢】書言
 ほおづき【酸漿・鬼灯】〔名〕ナス科の多年草。ふつう観賞用に人家に栽培される。高さ四〇~九〇センチ。根茎がある。葉には長柄があり、葉身は卵状楕円形で縁に大きな鋸歯(きょし)がある。長さ五~一二センチ。初夏、先が浅く五裂したさかずき形の小さな花が下向きに咲く。花は淡黄白色で中心部は緑色。果実は球形で袋状の萼(がく)に包まれて赤く熟す。子どもが種子を除いた果実の皮を口にふくんでならして遊ぶ。根は鎮咳・利尿薬に使う。漢名、酸漿。かがち。あかかがち。ぬかずき。学名は Physalisalkekengi《季・秋》*本草和名〔九一八(延喜一八)頃〕「酸漿〈略〉和名保々都岐 一名奴加都岐」*源氏物語〔一〇〇一(長保三)~一四頃〕野分「いとをかしき、色あひ・つらつきなり。ほをつきなどいふめるやうに、ふくらかにて」*文明本節用集〔室町中〕「茨菰 ホウヅキ 或云鬼燈其実赤如燈也」
ほおづき【酸漿・鬼灯】〔名〕ナス科の多年草。ふつう観賞用に人家に栽培される。高さ四〇~九〇センチ。根茎がある。葉には長柄があり、葉身は卵状楕円形で縁に大きな鋸歯(きょし)がある。長さ五~一二センチ。初夏、先が浅く五裂したさかずき形の小さな花が下向きに咲く。花は淡黄白色で中心部は緑色。果実は球形で袋状の萼(がく)に包まれて赤く熟す。子どもが種子を除いた果実の皮を口にふくんでならして遊ぶ。根は鎮咳・利尿薬に使う。漢名、酸漿。かがち。あかかがち。ぬかずき。学名は Physalisalkekengi《季・秋》*本草和名〔九一八(延喜一八)頃〕「酸漿〈略〉和名保々都岐 一名奴加都岐」*源氏物語〔一〇〇一(長保三)~一四頃〕野分「いとをかしき、色あひ・つらつきなり。ほをつきなどいふめるやうに、ふくらかにて」*文明本節用集〔室町中〕「茨菰 ホウヅキ 或云鬼燈其実赤如燈也」
*俳諧・芭蕉庵小文庫〔一六九六(元禄九)〕堅田十六夜之辨「鬼灯は実も葉もからも紅葉哉〈芭蕉〉」*大和本草〔一七〇九(宝永六)〕卷九「酸醤(ホホヅキ)〈略〉此草をほほづきと云は、ほほと云臭虫、このんで其葉につきて、食する故なり」*日本植物名彙〔一八八四(明治一七)〕〈松村任三〉「ホホヅキ 酸醤」口に入れ舌でおし鳴らすもの。ほおずきの実に小穴をあけ種子を出したものや、カラニシ、アカニシなど巻貝類の卵の袋から作るうみほおずきがある。*栄花物語〔一〇二八(長元元)~九二頃〕初花「御色白く麗しう、ほほづきなどを吹きふくらめて据ゑたらんやうにぞ見えさせ給」*評判記・吉原呼子鳥〔一六六八(寛文八)〕「御口にふくませたまひしほうづきを、とりをとし」*談義本・根無草〔一七六三(宝暦一三)~六九〕前・四「燈籠草(ホホヅキ)店は珊瑚樹をならべ、玉蜀黍は鮫をかざる」【語誌】『古事記』上卷に、八岐大蛇の眼をアカカガチのようだとして、「此に赤加賀知と謂へるは、今の酸漿ぞ」とあるところから、ホオズキの古名がカガチ・アカカガチであったことがわかる。の挙例『大和本草』には「ホホ(カメムシの類)」が葉に付いて食べるゆえの命名とあるが疑問。むしろ、ホホヅキのヅキは「カホツキ」、「メツキ」などの「ツキ」の連濁形か。の挙例「源氏」など見ると、ふっくらとした顔、あるいは頬からの連想と考える方が自然と思われる。口の中でキュウキュウとホオズキを鳴らすあそびはの挙例『栄花物語』に見られるように古くからのものである。また、丸い果に着物を着せて人形遊びをすることも多く、蕪村に「鬼灯や清原の女が生写し」の句もある。暑いさなかに美しい姿を長く保つところから、観賞用にも重宝され、江戸の街には多くのホオズキ売りが見られた。市日にホオズキを売ることは今日も行なわれており、七月九・一〇日浅草寺のホオズキ市は有名。【方言】螺(にし)類の卵。海ほおずき。《ほおずき》三重県 062591 男児の陰部。《ほおずき》京都市 054 植物、はないかだ(花筏)。《ほおずき》静岡県南伊豆 036《ほおずきのき〔─木〕》長野県北佐久郡 485 植物、みつばうつぎ(三葉空木)。《ほおずきのき》長野県佐久 485 植物、もっこく(木斛)。《ほおずき》愛媛県東部 008 周桑郡 036 植物、ちしゃのき(萵苣木)。《ほおずき》神奈川県 008 植物、みずおおばこ(水大葉子)。《ほおずき》香川県東部 037 植物、ほたるぶくろ(蛍袋)。《ほおずき》山口県玖珂郡・都濃郡 794【語源説】⑴人の頬に似ているところから〔俚言集覧・嬉遊笑覧・和訓栞・日本語源=賀茂百樹〕。⑵「ホホ(莢)」という虫がつくところから〔日本釈名・東雅・重訂本草綱目啓蒙〕⑶ふくらして弄ぶところから「ホホフキ(含々吹)」または、頬突の義か〔日本語源=賀茂百樹〕。⑷頬突の義〔国語の語根とその分類=大島正健・大言海〕。口に入れて、頬を突いて鳴らすところから〔滑稽雑談所引和訓義解〕。⑸「ホウヅキ(顋月)」の義か。赤く丸く月に似て、口中に含むところから〔和句解〕。⑹「オホヒイツクミ(掩斎実)」の義〔日本語原学=林甕臣〕。実の赤いところから、火々着の義〔古今要覧稿〕。⑺「ホホムチ(含血)」の義〔名言通〕。【発音】ホーズキオフヅキ〔豊後〕フーズキ〔長崎〕フーヅキ〔福島・茨城・佐賀・島原方言・豊後〕フズキ〔福井大飯〕フズ〔鹿児島方言〕フツキ〔信州読本・鹿児島〕フヅキ〔土佐・鹿児島方言・大隅〕フヅ〔鹿児島方言〕フンヅギ・ホンヅギ〔山形〕ホーズケ〔富山市〕ホーツキ〔埼玉・埼玉方言〕ホーヂク〔土佐〕ホズゲ〔津軽語彙〕ホゾキ・ホーゾキ〔石川〕ホヅゲ・ホンジキ・ホズゲ〔秋田〕ホジキ〔青森〕ホンジギ〔山形小国〕ホンズギ〔岩手・秋田〕平安との両様○ズ 【辞書】字鏡・和名・色葉・名義・下学・文明・伊京・明応・天正・饅頭・黒本・易林・日葡・書言・言海【表記】山茨菰(下学・伊京・明応・天正・饅頭・黒本・易林)酸漿(和名・色葉・名義・伊京・言海)洛神珠(色葉)酸醤(名義)茨菰(文明)百部根(伊京)苦灯籠草(書言)【図版】 酸漿 三項目ほおずきの花(はな)ほおずきの瓢(ひさご)ほおずきほどな=涙(なみだ)[=血(ち)の涙(なみだ)]
【辞書】字鏡・和名・色葉・名義・下学・文明・伊京・明応・天正・饅頭・黒本・易林・日葡・書言・言海【表記】山茨菰(下学・伊京・明応・天正・饅頭・黒本・易林)酸漿(和名・色葉・名義・伊京・言海)洛神珠(色葉)酸醤(名義)茨菰(文明)百部根(伊京)苦灯籠草(書言)【図版】 酸漿 三項目ほおずきの花(はな)ほおずきの瓢(ひさご)ほおずきほどな=涙(なみだ)[=血(ち)の涙(なみだ)]
ぬか-ずき[:づき]【酸漿】〔名〕「ほおずき(酸漿)」の古名。*新撰字鏡〔八九八(昌泰元)~九〇一(延喜元)頃〕「酸醤 五月採実陰干定心益気 加我彌吾佐 又云奴加豆支」*本草和名〔九一八(延喜一八)頃〕「酸漿 一名酢漿〈略〉一名酸芳草、和名保保都岐 一名奴加都岐」*枕冊子〔一〇C終〕六七・草の花は「夕顔は、〈略〉実のありさまこそ、いとくちをしけれ。などさはた生ひ出でけん。ぬかづきなどいふもののやうにだにあれかし」*俳諧・江戸新八百韻〔一七五六(宝暦六)〕「つくつくと喜怒哀楽の陰嚢玉〈存義〉 風生てぬるき糠つきの花〈亀成〉」【語源説】「ニガツキ(苦之木)」の転か〔大言海〕。その実が下をむき額突くような形であるところから〔嬉遊笑覧〕。「ヌカ」は小さいものの称。「ツキ」は「ホホツキ」の「ツキ〔千草の根ざし〕」。「ヌ」は発語。「カヅキ」は「加賀着」の中略〔古今要覧稿〕。【辞書】字鏡・言海【表記】酸醤・(字鏡)酸漿(言海)