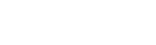俳諧『冬の日』〔一六八五(貞享二)〕に、
はなに泣 桜の黴と すてにける〈芭蕉〉
僧ものいはず 欵冬を呑〈羽笠〉
と言う連句がある。いま百花繚乱に咲き誇る「さくらはな」に思いの丈その思いを寄せる人の意には芭蕉のこの発句と羽笠の結句はどう映るのか、ふと考えて見たりするときでもある。さくらの樹木は、日本国中、津々浦々の見所を有している。咲き誇りの美しさに叛してその短さ故に人の心寄せも一層深さを増す。この世の中でご自身が一番愛でてみたいさくら樹はと問えば、ふるさとのさくらなのかもしれない。はたまた、心象深く見果てぬさくらの世界やもしれぬ。「坐光風月天地之春」の境地で目を閉じて景をこゝろの内に描き出すとき、「月訪ひの桜」(万葉人大伴家持が植えたという)が見えてくる。遠く立山連峰の白き雪景の山々に見守られ、そのさくらの蘖 に花を付けている(昭和七年の台風で倒れ原木はない)。雪深い黒部にも春のおとないを告げる感へと吾人のこゝろは夢見走りする。
この三月から、北陸新幹線は東京から金沢へと一飛びする。だが、人は地に足を踏みしめ、彼の地へ赴むかんとするとき、例しの古事を自今に向けておくことが必要となる。逆に多くの若者がますます都心東京圏に集中しようとしている。己れの居場所を求めなおすとすれば、修行期、活動期、伝授期まで渦巻きの渦中に向かわんとすることが誰しも必然なのである。
このことの動きを全て果たし終えた日に、この句を思い出してごらんあれ。「はなに泣き」は、花盛りの華やかなりしときもいつの間にか過ぎ去って帰らざりし盛りを思って泣き歎いていたのだという。だが、「桜の黴と」は、今眼前にあるのはもうあの「さくら花」ではなかった。それは、なんと「桜の木に着いた苔カビ」のようなものだと悟ったのだから、全てを罷めて棄てたのだという。と氣づいたとき、歩むべき道を見失わずやって来たことをこゝろから喜ぼう。萬法の教えを学ぶ修行僧は、何ももの言わず、ひたすら静かに健胃・痰切・咳止・疝気に効く欵冬 [山蕗の茶]を飲んだのだ。まだ、この境地に程遠いのだが、
はなに立 桜の鰕と 拾ひける 佛ものいはふ 甘茶そそぐ
と余興してみた。

フキタンポポ【款冬】