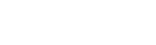一年の半分の月日がいつの間にか過ぎ、夏の季節が愈々本番へとむかっている。こんな折、人が離れ、人が結びつきを繰り返していく最中で「茶の湯」という作法は、どことなく心つむぎの架け橋を演出しているように思えてならない。時空を超えて古人と結び逢う世界が視覚聴覚に左右される書籍媒体であれば、「茶の湯」は視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚といった五感をもとに交わせる世界がここに存在する。
そして、茶好きな私は濃茶を所望し、茶盌の内側に残った茶を利用して薄茶を吞むといった二度茶盌に向き合うことが多い。遠慮なしにだ。一度ならず二度服す感覚は、同じ盌の内に別なる感覚を読み取ることが行われているからだと思えてならない。
今、自身では果たし得たことを再度改めて見直す。時を置いてこれを見直すことで、その成し得たなかにも新たなる見つめ直したい目が動きだす。その機会を人から与えていただくことになれば、その至福は倍増し、感謝の念も一入深みを増すものとなってくる。
大学は、個の集合体であると共に、連携と統合が充分機能する場であり続けてきている。この一つの組織ですら、既に対外交流の推進を臨まれ、産学共同研究プロジェクト化が次なる未来の教育現場思考へと展開しようとしてきている。
私の身近なところでも、言語文化研究とスポーツ身体科学研究とが融合して統合化が目論まれている。この統合化に立体性で構築し、火を頂点に水あり空気あり土ありの原点を数理的に読み取る能力をふんだんに発揮できるときが近づいているようだ。
だとしても そこまでやる氣 ことばかり
 【補記】
【補記】
濃茶は「練る、薄茶は「点てる」その違ひをこの夏、是非ご」堪能あれ。いただくにあたり、茶菓子には、「梅香の滴」もちいてみる、つゆはらいとなせば、これはれやかなる心となり笑みもます。葛と梅酒のハーモニーが織りなす香りただよはんかな。二度吞みの境地、やがてあらわれなむ。午後の茶を嗜みながら、こゝろの癒しどころになればとことのべん。
京都茶寮にて