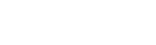「負」字の話しをしたい。世の中、AがあればBがある。どちらか一方が力を蓄えたとき、その「力」を周囲を巻き込んでも格外に布散しようとする。この方法が同時に起こることもあれば、一方が先に仕掛け、もう一方がこれに対応することもある。
この拮抗した「力」が大きければ大きいほど、周囲はその渦に巻き込まれ、損破が拡大し、此を元に修復する作業は、これまた蘇生させようとするための新たな「力」が必要となることを人は歴史という歴録を以て理会してきているはずなのだが。
国と国といった「戰争」は、此の「力」の布散に他ならない。この「余剰化」しようとする、癒した「力」でどう沈静化する「特効薬」は、これまた容易でないものかもしれない。
時にスポーツ競技、時にはゲームなどのルールを設けて、そのなかで勝敗を決定づけることで勝ち負けを意識するに留めてきた。この勝敗も、その結果に一喜一憂する人の数が規模を増せば、やはり「力」の拡散が発生する。このときに用いることばにも「たたか・う【闘・争】」「あらそ・う【爭】」と用いる。そして、勝てば「優勝」(複数)、「王者」「覇者」(単独)と呼称されもする。では、ピラミッドの頂点ともいう座につけなかった多くの敗者はどう位置づけられてきたのだろうかと誰もが素朴の疑問は持ち得ているのではないか。その一つには、次に勝者になれるようにたゆまぬ氣力・努力・鍛練・技能を磨くことに向かっていく。その結果、何度も何度も引き下ろされる姿も見えてくる。その向きあう姿勢を「負」と云い、「まけ」「おう」と呼称し、その「負」の姿勢は、連鎖性などを見ていくと、軈て「かたり」が生まれ、物語すなわち「文学」となって昇華していく。
吾人は、この流れを「非運」と呼んいる。「ヒウン」と口にのぼらせたとき、「悲運」と「非運」の二種表記が当然あること、そのなかで客観視するのであれば「運、あらず」の「非運」となる。当事者に近いものであれば、「かなしみをはこぶ」の「悲運」と主観視するだろう。
その「非運」の「負」を、別仕立てで、「負けん氣が強い」「負け惜しみ」「負けず嫌い」などの動態性のことば表現にして用いて、身近のところであれば「姉妹」、「兄弟」がその対象人として浮上する。「二番は嫌だ」「負けて悔しい」のと、どの道であれ、勝つ喜びを知ることも大切にしたいのだが勝つ者にも、「優勝の「優」はやさしいと書くんだね、本統の優しさが足りないと、一番にはなれないんだよ」の氣持ちを学ぶことになる。その上で、多くの「負」をどう見切るかということにも注目したい。< 「負け惜しみ」を口にする、やはり、寓話に数あり、その一話に『イソップ物語』の現代版「狐と葡萄」の狐のことばには、「どうせこんなぶどうは酸っぱくてまずいにきまってる。誰が食べてやるものか。」(明治版では「ヨシ、なんだこんなものを、葡萄はすツぱいぞ」とする)
「負け惜しみ」を口にする、やはり、寓話に数あり、その一話に『イソップ物語』の現代版「狐と葡萄」の狐のことばには、「どうせこんなぶどうは酸っぱくてまずいにきまってる。誰が食べてやるものか。」(明治版では「ヨシ、なんだこんなものを、葡萄はすツぱいぞ」とする)
これを社会心理学では、「認知的不協和」の例とする。英語には、この寓話を元にして生まれた熟語として「Sour grapes」とあるが、これは当に「負け惜しみ」を意味する。「負け惜しみを言う」が「cry sour grapes」と云い、「負け惜しみを言う人のことは、「Sour loser」や「bad loser」と云う。
日本の古辞書、観智院本『類聚名義抄』〔尸部法下九一頁八2〕

とあって、和訓(1)「オフ」(2)「マク」(3)「ソムク」(4)「タノム」(5)「アリ」と云った動詞語がならぶ。 末尾の「あり」の意義は、今は不詳。

同じく、『名義抄』〔貝部廿四・佛下本末一七頁二ー4/三ー1〕として、和訓(1)「オフ」(2)「ソムク」(3)「トシ」(4)「タノム」(5)「ウレヘ」(6) 「ハヂ(ツ)」(7)「オホス」(8)「マク」とあって、此方も(3)「とし」を除く語は動詞語群となっている。そして、(5)「ウレヘ」と(7)「オホス」の語が増えている。このように「貝部」と「尸部」とでは、同じ文字でもその扱いが異なっている。こうしたなかで、和語「たの・む」の語は何かしらの未来を暗示しているようにも見えてくる。如何、そして、佳い年を迎えるための準備のときになってきた。